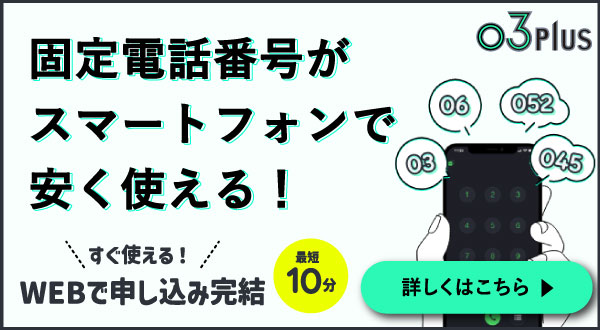【まとめ】固定電話の種類別の料金・契約方法を解説!固定電話廃止の詳細も

従来、法人ではNTTから市外局番付き電話番号を取得して、固定電話で電話業務を行うのが一般的でした。市外局番付き電話番号は社会的信用が高く、法人登記や銀行口座開設に使えるなどのメリットがあるため、法人で使われてきたのです。しかし近年、IP電話サービスでも市外局番付き電話番号を取得できるようになっていることから、乗り換えを検討する法人も増えています。
そこで今回は、固定電話とはそもそもどういうものなのか、種類ごとの特徴や料金、契約方法、固定電話の廃止についての詳細を解説していきます。
目次
固定電話の基礎知識
固定電話とはどのようなものなのか、まずは基礎知識としてその歴史やメリット・デメリットについて解説していきます。
固定電話とは
固定電話とは電話が登場してから使われてきたもので、アナログ回線(銅線による通信網)によって提供されていた通話サービスのことです。
アナログ回線を使用する固定電話で通話を行う仕組みは、次のとおりです。
発信側が電話番号を入力すると、信号が発信されて発信側の最寄りの電話局へそれが送られます。中継回線によって着信側の最寄りの電話局に信号が到達すると、着信側の固定電話機の呼び出し音が鳴ります。呼び出し音を受けて着信側が受話器を取ると回線が接続され、通話ができるようになります。
ちなみに「固定電話機」とは、据え置き型の端末のことで、従来はアナログ回線に接続して利用されていました。
アナログ回線は2024年1月に廃止されてIP網へと移行されました。そのため、現在の固定電話は、通話で従来のアナログ回線(銅線)を用いることはありません。
固定電話の歴史
日本における固定電話の歴史は、およそ150年前の1869年(明治2年)10月23日からスタートします。最初は、東京・横浜間の電信線架設工事から着手されたそうです。架設工事の着手から20年以上経過した1890年(明治23年)に日本初の電話サービスがスタート。当初の加入者数は東京で155世帯、横浜で42世帯の合計197世帯しかありませんでした。
開通当初の電話料金は、当時の値段で月額40円であり、現代に置き換えるとおよそ15万円です。通話料は月額料金を支払うことで無料でしたが、とても一般庶民が払える額ではありません。
1900年(明治33年)になると、上野・新橋の駅構内に2箇所、京橋に1箇所公衆電話ボックスが登場します。さらに1933年(昭和8年)になると、電話マークの元になった黒電話が登場します。さらに1985年(昭和60年)には通信事業が民営化されたことを機に、各家電メーカーが参入してきました。さまざまなデザインで多機能な固定電話機が数多く発表されています。コードレス化や子機の登場は、現代のスマホや携帯電話の源流を感じさせます。
公衆電話も昭和以降、さまざまな変化を遂げていきます。1953年(昭和28年)の「赤電話」、1968年(昭和43年)には電話ボックスで利用できる「青電話」、1972年(昭和47年)には100円硬貨が利用できて長距離電話をかけやすくなった「黄電話」が登場します。ちなみに、「黄電話」は100円を投入した場合、100円分に満たない通話をした場合でもおつりはでてきません。そのため、時間いっぱい話さないともったいない気がする人も多いようでした。1982年(昭和57年)になると、硬貨ではなく磁気カードのテレホンカードを利用できるカード式公衆電話が登場します。アイドルテレカがマニアの間で高額売買され、一大ブームとなりました。
さらに1990年(平成2年)にはISDN回線が使われているデジタル公衆電話が登場します。データ通信や画像通信などができるため、外出中のビジネスマンが急ぎの仕事で利用することも多かったようです。
そしてときは流れて2024年1月、それまで使われてきたアナログ回線は廃止され、IP網へと移行することとなりました。
固定電話のメリット
固定電話を利用するメリットには以下のようなものがあります。信頼されやすい
固定電話を会社代表番号にしている企業は信頼されやすい傾向にあります。固定電話に使用される電話番号は市外局番付き電話番号です。番号には利用者の地域情報が含まれているため、会社が実在しているかどうかが電話番号のみで判別できます。そして古くから使われておりなじみある形式の電話番号であるため、信用を得やすい傾向にあります。 反対に携帯電話番号や050から始まるIP電話番号だと、会社が実在しているかどうかが分かりません。そのため、電話番号のみの信用度としては固定電話で使われる市外局番付き電話番号が最も高いと考えられています。
セキュリティが高い
固定電話は高セキュリティであることもメリットの一つです。固定電話は前述の通り、電話回線を使用して通話を行います。通話を行うためのみの回線ですので、固定電話を通してデータベースにアクセスすることはできません。そのため、ウイルス感染やサイバー攻撃などによる情報漏洩リスクがないのです。 また、固定電話は通話以外には使い道がありませんので、コンピュータのように不正利用したり通信端末を私物化したりするといったことも防げます。これは企業統治の強化につながるものです。
固定電話のデメリット
固定電話の利用にはメリットがありますが、デメリットもあります。
導入に時間やコストがかかる
固定電話を新たに設置する場合、回線の引き込みや通信装置の設置をするための開通工事をしなければなりません。業者のスケジュールにもよりますが、数週間待たされることもあります。また、固定電話機や必要に応じてPBXの購入が必要で、まとまった費用が必要です。回線を利用するためには施設設置負担金と呼ばれる費用の支払いもあります。
移転時に電話番号が変わる
スマホの場合はどこに引っ越ししても事業者を変更しなければ番号が変わることはありません。しかし固定電話の番号は市外に移転する場合に変更されてしまいます。電話番号を変更になってしまえば、公式サイトや名刺、広告物の記載変更が必要ですし、取引先や顧客に周知しなければなりません。そのため、多大な手間や費用がかかります。
オフィス内でしか利用できない
固定電話は基本的にオフィス内でしか利用できません。例えば従来のビジネスフォンの場合、PBXが設置されたオフィス内でしか内線・外線は行えません。そのため、外出中や自宅でリモートワークしている場合はスマホで電話対応する必要があります。
法人で使われる固定電話の「4つの種類」
法人で使われる固定電話には「アナログ回線」「ISDN回線」「直収電話」「光IP電話」の4種類があります。ここではそれぞれの概要を解説します。
NTT加入電話
NTT加入電話とは、NTT東日本・西日本で提供されているアナログ回線の固定電話サービスです。「東京03」「大阪06」などの市外局番付き電話番号を取得できます。戦後から存在する固定電話サービスであり、導入するためには電話加入権という設置負担金が必要でした。現在は固定電話サービスがいくつか登場し、それに伴ってNTT加入電話でも設置負担金不要のプランがあります。
NTT加入電話にはアナログ回線とISDN回線の2種類があり、それぞれ違った特徴を持ちます。
アナログ回線
アナログ回線では、NTTが提供するアナログ信号を受信して通話を行います。1契約で1回線のみしか使用できず、電話しか使わない、またはFAXと電話を別に使用するようなケースではランニングコストを抑えやすいため、利用されることがあります。
アナログ回線は銅線に音声をのせて通話を行う形式であり、ISDNや光回線より通話品質がやや劣ることもあります。その一方で、アナログ回線はISDNと同様に、停電時にも使用でき、災害時などのトラブル時に強いのが特徴です。
ISDN回線 ※2024年1月にサービスが終了しました。
ISDN回線はデジタル信号により通話を行います。1契約で2回線利用でき、電話とFAXを同時に利用したいケースで利用されます。
ISDNの特徴は音声をデジタルデータに変換して銅線で送信することです。デジタル変換されることで、アナログ回線よりも簡単に盗聴されにくく通話音質も良いというメリットがあります。
直収電話
直収電話とは、NTT東日本・西日本以外の業者が提供している固定電話サービスのことです。NTTが使用していない予備回線を使用し、事業者独自の通信設備によって通話を行います。そのため、業者ごとに独自のサービスが提供されているのが特徴です。NTTに基本料や通話料を支払う必要はないことから、加入電話に比べて基本料や通話料が安いです。
光電話
光電話は光ファイバー回線を使用して通話を行うIP電話のことです。1回線で電話とインターネットを使えるため現在、急速に普及しています。
インターネット通信を行える光ファイバーを使用するため、加入電話と比べて通話料金がリーズナブルで、通話距離に関わらず全国一律であることが大きな特徴です。また、通信速度が速く安定しているため、通話音質も高いです。
4種類の特徴・デメリットを比較
法人で使われる4種類の固定電話サービスのメリットやデメリットを、表にして簡単に比較してみました。
|
|
メリット |
デメリット |
|---|---|---|
| アナログ回線 | 1契約1回線であり、電話のみを使うケースでは費用を抑えやすい。災害にも強いのが特徴。 | 電話とFAXを同時に使いたいケースでは、2契約必要なのでコストパフォーマンスが悪い。通話品質がISDNや光回線と比べてやや劣ることがある。 |
| ISDN回線 ※サービス終了 |
1契約で2回線使えるため、電話とFAXを同時に使うケースで利用価値がある。音声をデジタル変換して伝えるため盗聴リスクが低く、通話品質も良い。 | 2024年1月にサービスが終了。 |
| 直収電話 | 事業者ごとに独自のサービスが提供されている。NTTに支払う料金がなく、加入電話よりも基本料・通話料が安い。 | 提供会社以外のサービスは受けられず、NTTで使えていたサービスも一部利用できないことがある。 |
| 光電話 | 光ファイバー回線を使用していてアナログ回線よりも基本料・通話料が安い。通信速度が速く安定しているので、通話音質も高い。インターネットも同時利用できる。 | 光ファイバー回線のインターネット契約が必要。インターネット回線を使用することから、停電時には通話できない。 |
話題になっている固定電話の「廃止」とは?
「2024年1月に固定電話が廃止された」という話を耳にしたことがある人も多いのではないでしょうか。
結論、正確には固定電話という存在はなくなっていません。具体的には、固定電話が利用する回線が、従来のアナログ回線からIP網へと切り替わったことを指しています。
ではこのIP網への移行とはどのようなことなのか、詳しく解説します。
IP網へ移行する背景
携帯電話の普及移行、固定電話の契約件数が減少していることや、回線設備が老朽化しているため、IP網に切り替わることが決定されました。実際に、中継交換機は2025年頃にはその機能を維持できなくなるとされています。
IP網へ移行前後の通話料を比較
固定電話の回線がアナログからIP網に切り替わったことで、通話料にはどのような変化があるのでしょうか。移行前後の通話料を比較してみましょう。
固定電話からの発信
- 従来の固定電話:8~23時:9.35円/3分(市外通話は11円/45秒)、23~8時:9.35円/4分(市外通話は11円/90秒)
- IP網移行後:9.35円/3分(時間帯・距離に関わらず全国一律)
従来、固定電話の通話料は、通話先への距離や通話を行う時間帯によって変動していました。しかしIP網へ移行後は、固定電話の通話料は距離や時間帯に関わらず、全国一律価格の「3分9.35円」になりました。基本料金はIP網移行後も変わりませんが、毎月のコストは安く抑えられるようになっています。
公衆電話からの発信
- 従来の固定電話:8~23時:8~56秒/10円、23~8時:13.5~76秒/10円 ※通話時間は距離により変動する
- IP網移行後:9.35円/3分(時間帯・距離に関わらず全国一律)
従来、固定電話の通話料は、通話先への距離や通話を行う時間帯によって変動していました。しかしIP網へ移行後は、固定電話の通話料は距離や時間帯に関わらず、全国一律価格の「3分9.35円」になりました。基本料金はIP網移行後も変わりませんが、毎月のコストは安く抑えられるようになっています。
IP網移行のメリット・デメリット
IP網に移行するメリットはさまざまあります。まず挙げられるのは前述の比較からも分かるように、通話料金が全国一律になることです。遠距離通話も安心して行うことができるでしょう。次に、高速通信が可能になることもメリットです。IP網ではノイズの少ない作動伝送が採用され、通話品質が良くなります。また、通話とともに動画やテキストなどのデータ通信も行えるため、将来的にはさまざまなサービスが提供される可能性があるでしょう。
デメリットとしては、ISDNディジタル通信モードが使用できなくなることです。ISDN回線そのものがなくなるわけではないものの、POSシステムや銀行ATMなどのサービスが利用できなくなる可能性があります。2027年頃までは補完策が提供されるとのことなので、ディジタル通信モードを使用するサービスを利用している事業者は、なるべく早めの対応を進めることが求められます。
NTT加入電話のメリット・デメリット、導入手順
ここからは、法人で利用される固定電話の契約方法別に、メリットとデメリット、そして導入の手順についてご紹介します。
まず、NTT加入電話にはどのようなメリット・デメリットがあるのか、さらに導入手順についても解説します。
NTT加入電話のメリット
・全ての番号にかけられる
0AB-J型、050型、携帯電話、特殊番号など全ての電話番号にかけられます。
・停電時も利用できる
電話機が電源を使用しないタイプ、または独自の電源が確保できている場合は停電時でもアナログ回線を使用して通話できます。
・災害時に優先通話できる
発信のみですが、災害時に優先的に通話できます。
・通話品質が安定している
IP電話よりも通話品質が高く安定している傾向にあります。
NTT加入電話のデメリット
・初期費用が高く導入に手間がかかる
新規契約の場合は設置負担金や契約料がかかります。また、電話回線の敷設工事が必要です。
・ランニングコストが高い
基本料金や通話料金がIP電話よりも高いです。また、遠距離通話は割高になります。
・固定電話機の購入や設置場所確保が必要
アナログ回線やISDN回線に対応した固定電話機を用意し、それを置く場所も確保しなければなりません。
NTT加入電話の導入にかかる料金
NTT加入電話導入時には以下の費用がかかります。
- 設置負担金:39,600円(税込)
- 契約料:880円(税込)
- 回線使用料(プッシュ回線):1級取扱所2,640円(税込)、2級取扱所2,640円(税込)、3級取扱所2,750円(税込)
NTT加入電話を新規導入する場合、トータルで40,000円ほどの初期費用が必要です。初期費用を抑えたい場合は「加入電話・ライトプラン」を選ぶことで設置負担金が不要となります。ただし、回線使用料が割高になるため、長期利用する場合はコストパフォーマンスが悪いです。
NTT加入電話の導入手順
NTT加入電話の申し込みをする前に、運転免許証などの身分証明証を用意しましょう。申し込みはNTT東日本・西日本のWEBサイトへの接続、または局番なしの「116(携帯電話からの場合は別の番号)」へ電話をして行います。住所を確認した後、担当者から伝えられた市外局番付き電話番号の候補から好きなものを選びます。工事が必要であれば、日程調整も行います。
工事は申し込みから1週間程度で行われるのが一般的です。ただし、業者のスケジュールによって変動することもあります。
直収電話のメリット・デメリット、導入手順
直収電話のメリット・デメリット、導入手順について解説します。
直収電話のメリット
初期費用が安い
設置負担金が不要になるため、導入時の費用を抑えられます。
基本料・通話料が安い
NTTの回線を使用しないため、基本料金や通話料が数%程度安くなります。長期的にみるとコスト面で大きなメリットです。
直収電話のデメリット
インターネット回線が利用できなくなる可能性がある
NTTのアナログ回線によりADSLを利用している場合、インターネットが使えなくなることがあります。
一部の番号に発信できない
NTTのサービスから外れるため、0120など一部の特殊番号に発信できなくなります。
直収電話の導入にかかる料金
直収電話の導入費用はサービスを提供している事業者ごとに異なります。初期費用が無料のところもあれば、数千円~数万円程度かかることもあるようです。基本料や通話料とあわせて、事前に確認しておきましょう。
直収電話の導入手順
まずは現在住んでいる住所が、申し込み予定の直収電話のサービス提供エリア内か確認しましょう。その後、直収電話の事業者または販売店に連絡し、契約内容について説明を受けます。申込用紙に必要事項を記入し署名捺印したら、後日事業者より申込受付の郵便が送られてきますので確認しましょう。
光IP電話のメリット・デメリット
光IP電話のメリット・デメリットを簡潔に紹介します。
光IP電話のメリット
基本料・通話料が安い
加入電話に比べてランニングコストが安く済みます。通話料は時間帯・距離に関わらず全国一律です。
通話品質が高い
安定した高速通信で、通話品質も高いです。
インターネット回線も利用できる
電話とともにインターネット回線も利用できます。
光IP電話のデメリット
光回線の契約が必須である
光回線契約をしなければ利用できません。
発信できない番号がある
一部の特殊番号に発信できません。
停電時は利用不可
光回線を使用するため、停電時には利用できません。
光IP電話の導入にかかる料金
NTTのフレッツ光ネクストオフィスタイプ(スタンダード)をビル・マンションで利用する場合、以下の導入費用がかかります。
初期工事費用:16,500円(土日休日工事の場合は3,300円上乗せ)
契約料:880円
NTT加入電話と比べると、初期費用はそれほど高く付きません。月額料金や通話料金が安く抑えられやすいことから、お得感があります。ただし、別途インターネット回線の月額料金もかかります。
光IP電話の導入手順
光IP電話の申し込みはNTT東日本・西日本のWEBサイトまたは電話にて行います。申込後、担当者から電話番号の候補がメールまたは電話にて送られてきます。その中から好きなものを選びましょう。
光回線が未導入の場合は、工事が必要です。工事日は申込後2~3週間程度の都合の良い日に設定するのが一般的ですが、繁忙期はもう少し伸びることもあります。土日祝日に工事を行う場合は追加費用として3,300円が必要です。
IP電話の利用もおすすめ
固定電話というと、NTT加入電話や光IP電話を思い浮かべる方が少なくありません。しかし、導入コストが高く工事の手間もかかるのが大きなデメリットです。そこでおすすめなのがIP電話による市外局番付き電話番号の取得です。
IP電話とは?
IP電話とは、インターネット回線を利用して通話を行うサービスのことです。サービスを提供しているベンダーによっては、市外局番付き電話番号も取得できます。スマホやPCなどインターネットに接続できる端末にアプリを導入することで利用でき、外出先からも取得した電話番号で発着信可能です。
IP電話のメリット
導入コストや手間がかからない
IP電話は申込後、アプリを導入することですぐに利用開始できるので手間がかかりません。また、初期費用はかかりますが、NTT加入電話の設置負担金ほどは高くないことがほとんどです。
基本料金や通話料金がリーズナブル
NTT加入電話と比べると、基本料金・通話料金がリーズナブルです。
外出先でも固定電話番号で電話対応できる
アプリを導入すればスマホから固定電話番号を使って発着信できます。いつでもどこでも電話対応でき、折り返し電話も固定電話番号を使って行うことが可能です。
リモートワークにも対応可能
スマホ・PCなどの端末で固定電話番号を使った発着信を行えるため、場所を問わず電話対応できます。そのため、リモートワークにも対応可能です。
人員の増減に合わせて柔軟に対応できる
企業規模や人員の増減に合わせ、回線数を柔軟に調整できます。
ビジネスに便利な機能を利用できる
インターネット回線を使用するサービスであり、通話録音、IVR、CTIなどさまざまな機能を利用できるのも特徴です。
IP電話と固定電話の違い
アナログ回線の固定電話は据え置きタイプの電話機を使用するため、機器が設置されたオフィス内でしか通話を行えません。外出時に電話を受けたい場合には、転送設定をする必要があります。また、導入には高額な設置負担金が必要で、配線工事の手間もかかります。
一方、IP電話はスマホやPCなど、インターネット回線を利用できるさまざまな端末で通話できます。そのため、外出先や自宅でも会社代表番号を利用して、オフィスにいるのと同じように電話対応が可能です。アプリをインストールすることで利用できるため、配線工事の必要もなく、人員の増減にも柔軟に対応できます。
IP電話の導入方法
IP電話に申し込む際には、アプリやWEBサイトから行います。ベンダーによっては書類手続きが不要で、アプリ上で本人確認が可能です。例えば「03plus」ならば、アプリでの申し込みから最短10分で市外局番付き電話番号を取得できます。
まとめ
今回は法人で使われる固定電話の種類や、それぞれの特徴・メリット・デメリットを解説しました。
企業において、市外局番付きの電話番号は社会的信用が高いことから、携帯電話ではなく固定電話を導入するのが一般的でした。しかし、導入コストや手間・時間がかかることから、近年はIP電話を導入するケースが増えています。
03plusならば、「東京03」を始めとした全国主要46局の市外局番付き電話番号を取得可能です。導入時のコストや手間もかからず、最短10分で利用を開始できます。また、通話録音やクラウドFAX、IVRや留守レポといった便利な機能も利用できますので、業務効率アップも実現可能です。
固定電話番号の取得を検討されているならば、ぜひ03plusをご検討ください。
03plusについて詳しくはこちら